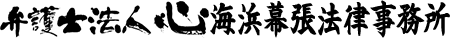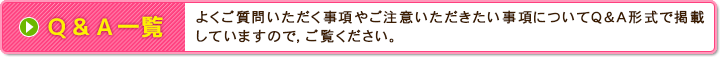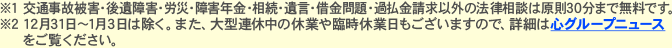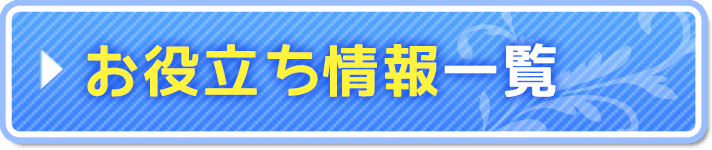相続人に遺留分を渡したくない場合の対策は?
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められているため、被相続人が、特定の推定相続人について遺言書で相続分を「ゼロ」と指定しても、後から遺留分相当額を取り返されてしまう可能性があります。
しかし、どうしても遺留分さえ渡したくない推定相続人がいる、と被相続人が考えるケースがあるかもしれません。
相続人の遺留分をはく奪する、あるいは遺留分を減らすためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、遺留分を渡したくない推定相続人がいる場合の対策を、法的な観点から解説します。
1 遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続できる財産の最低保障額を意味します(民法1042条1項)。
被相続人は、遺言書や生前贈与により、自身が所有する財産を自由に譲り渡すことができるのが原則です。
その一方で、相続人の相続に対する期待を一定程度保護するため、遺留分相当額については、相続権が実質的に保障されています。
遺留分未満の財産しかもらえなかった相続人は、遺産を多くもらった者に対して「遺留分侵害額請求」(民法1046条1項)を行うことができます。
遺留分侵害額請求が認められると、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けられるのです。
2 相続人に遺留分を渡さない方法
例えば、被相続人にとって気に入らない相続人がいて、遺留分さえも渡したくないと考えるケースがあるかもしれません。
法的には、きわめて限られた場合ではあるものの、相続人に全く遺留分を与えない方法がいくつか存在します。
⑴ 対象推定相続人(遺留分権利者)に、遺留分を放棄してもらう
遺留分は、遺留分権利者の意思によって放棄することが認められています(民法1049条1項)。
被相続人が生前の段階で、遺留分権利者にあらかじめ遺留分を放棄してもらえば、相続発生後に遺留分相当の財産を渡す必要はありません。
ただし、遺留分の放棄は、あくまでも遺留分権利者の自発的な意思によって行われるものです。
そのため、被相続人や他の相続人が圧力をかけて、無理やり遺留分を放棄させることはできません。
また、相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けて初めて有効となります。
家庭裁判所は、以下の各点を考慮したうえで、遺留分の放棄の有効性を判断します。
- 遺留分の放棄が、本人の自由意思に基づいているかどうか
- 遺留分を放棄する理由に、合理性と必要性が認められるかどうか
- 遺留分を放棄することの代償が与えられているかどうか
特にポイントとなるのが、「遺留分を放棄することの代償が与えられているかどうか」という点です。
「代償」として認められるのは、原則として、遺留分相当額と同等以上の生前贈与に限られます。
したがって、被相続人が生前の段階で遺留分を放棄させるには、結局遺留分並みの価値を持つ財産(ないし、遺留分権利者が納得する財産)を与えなければなりません。
このような点を考慮すると、遺留分権利者が納得するだけの財産が、遺留分相当額より低くない場合は、「遺留分を渡したくない」という目的のために、遺留分を放棄させることを試みるのは、実効性に乏しいと言えるでしょう。
⑵ 相続欠格に該当する相続人=遺留分を失う
重大・悪質な非違行為のあった相続人は、「相続欠格」(民法891条)によって相続権を失う場合があります。
相続欠格により相続権を失った相続人は、同時に遺留分も失います。
相続欠格に該当するのは、以下の5つの場合です。
- 1. 被相続人・先順位相続人・同順位相続人のいずれかを故意に死亡させ、または死亡させようとしたために、刑事罰を科された場合
- 2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴をしなかった場合(是非の弁別がない場合、および殺害者が自己の配偶者または直系血族の場合を除く)
- 3. 詐欺または強迫によって、遺言やその撤回・取り消し・変更を妨げたこと
- 4. 詐欺または強迫によって、遺言をさせ、または遺言の撤回・取り消し・変更をさせたこと
- 5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したこと
相続人が上記のいずれかに該当する場合には、その相続人に遺留分相当の財産を渡す必要はありません。
なお、相続欠格の効果は、被相続人が特に申立てなどを行わなくても、法律上当然に発生します。
⑶ 相続廃除の申立てを行う
相続欠格に該当しないケースでも、被相続人が「相続廃除」(民法892条)を申し立てることにより、相続人の相続権をはく奪できる場合があります。
相続廃除により相続権を失った相続人は、相続欠格の場合と同じく、遺留分も失うことになります。
相続廃除に該当するのは、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えるなど、著しい非行があった推定相続人です。
なお相続廃除は、相続欠格とは異なり、被相続人の申立てに基づく家庭裁判所の審判によって効力を生じます。かかる申立ては、被相続人の生前における申立は勿論、遺言による申立も可能です。
また、相続廃除については、被相続人の意思によって、いつでも家庭裁判所に取り消しを請求することが可能です(民法894条1項)。
⑷ 遺言書の付言事項
遺言書には、財産の分け方に関する記載とは別に、親族へのメッセージなどを記載することもできます。
これを「付言事項」と言います。
遺留分を渡したくない推定相続人がいる場合には、その推定相続人への遺産配分をゼロとしたうえで、「遺言書の内容を尊重して、遺留分侵害額請求を行わないように」というメッセージを付言事項に記載しておくことが考えられます。
付言事項には法的拘束力がありませんが、相続人の感情に訴えかけることはできますので、結果的に遺留分に関するトラブルを回避できるかもしれません。
ただし、あくまでも事実上の「お願い」に留まるため、付言事項を無視して遺留分侵害額請求が行われた場合には、それを阻止することはできない点に注意しましょう。
3 相続人の遺留分を減らす方法
これまで見てきたように、相続人の遺留分を完全にはく奪する方法は、利用できる場面が限定的であったり、法的拘束力がなかったりして、実現性が高いとは言い難いのが実情です。
しかし、遺留分を全く与えないことは難しいとしても、生前の遺留分対策により、相続人の遺留分を減らすことはできる場合があります。
相続人の遺留分を減らすために考えられる主な対策は、以下のとおりです。
⑴ 養子縁組をして1人当たりの遺留分を減らす
被相続人が養親として養子縁組をすると、養子は相続において、被相続人の「子」として取り扱われます。
その結果、実子に与えられるはずだった相続分は分散し、それに伴って遺留分も減ることになります。
たとえば、配偶者と子Aが相続人であるとします。
この場合、子Aの相続分は2分の1、遺留分は4分の1です。
上記のケースで、被相続人がBと養子縁組をしたとしましょう。
養子縁組により、被相続人の「子」は2人になります。
そのため、子Aの相続分は4分の1、遺留分は8分の1に減ります。
このように、実子の遺留分を減らしたい場合には、養子縁組によって「子」の人数を増やすことが有効となることがあります。
ただし、養子縁組による遺留分対策を行うと、遺留分を渡したくない者以外の子の相続分・遺留分も減ってしまいます。
また、実質的な親子関係を形成する意思がない場合には、養子縁組が無効とされてしまうおそれがある点にも注意が必要です。
⑵ 生前贈与をして相続財産を減らす
相続人の遺留分額を減らすためには、生前贈与を行って、相続財産自体の金額を減らす方法も考えられます。
ただし、相続人に対する贈与は10年間、相続人以外の者に対する贈与は1年間、相続開示時点から遡って遺留分計算の対象になります(民法1044条1項1文、3項)。
よって、生前贈与による遺留分対策は、被相続人が健康なうちに、かなり早い段階から着手することが必要です。
また、遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた生前贈与は、上記の期間より前に行われたものについても、遺留分計算の対象に含められてしまいます(民法1044条1項2文)。
そのため、生前贈与による遺留分対策を行う際には、その効果が後で否認されないように、弁護士に相談しながら慎重に対応することをお勧めいたします。
⑶ 生命保険に加入して掛け金を支払う
遺留分計算の基礎となる相続財産の金額を減らすには、生前贈与のほか、生命保険を活用する方法も考えられます。
生命保険から支払われる死亡保険金は、受取人の固有財産であり、相続財産ではないと解されています。
したがって、被相続人が生前の段階で生命保険に加入し、掛け金を拠出することで、実質的に相続財産を減らすことができるのです。
ただし、あまりにも高額の生命保険をかけた場合、保険金請求権の額面が特別受益とみなされ、遺留分計算の基礎に持ち戻される可能性があるので、保険契約の設定には注意しましょう(最高裁平成16年10月29日決定)。
4 生前の遺留分対策・相続対策は弁護士にご相談を
以上から、相続人に認められた権利である遺留分を、はく奪したり、その金額を減らしたりすることは容易ではありません。
しかし、被相続人が生前の段階で実施できる遺留分対策も、状況によってはいくつか考えられます。
ご自身の置かれている状況に応じて、適切な遺留分対策を講じるためには、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
弁護士は、遺留分対策を含めて、次世代へ円滑に財産を引き継ぐための方法につき、多角的な観点からアドバイスいたします。
被相続人となる方のご意向や、相続人のご都合・利便性などを考慮して、どのような形の相続が望ましいか、依頼者とともに真摯に考えて参ります。
生前の遺留分対策・相続対策は、当法人の弁護士にご相談ください。